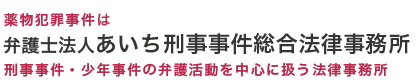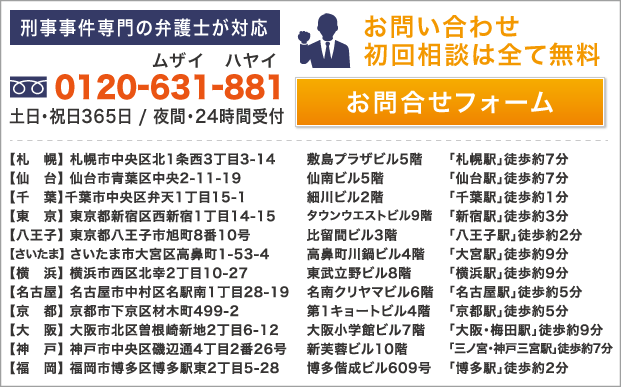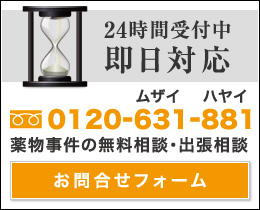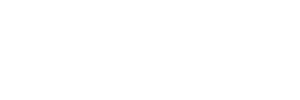執行猶予にして欲しい
※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
執行猶予
執行猶予とは、検察官により起訴された被告人が、刑事裁判において3年以下の拘禁又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により裁判所が1~5年の期間を定め、その間被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
しかし、執行猶予がつけられるのは、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者又は前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者であること、もしくは前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が2年以下の拘禁又は拘禁の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに限られます(執行猶予の要件については下記参照)。
執行猶予は、これまで犯罪に関わったことがない、再犯のおそれが少ないなどの場合につけられます。犯罪の内容が悪質だったり、犯罪歴があったりする場合は、執行猶予付き判決を期待することは難しくなります。
執行猶予付き判決を受けると、普通の社会生活に戻ることができるので、無罪になったと思い違いをする人もあるようですが、決して無罪になったわけではなく、拘禁刑の執行が期限付きで保留されているわけです。
もし、期限内に再び犯罪に関わって逮捕されるようなことがあれば、執行猶予は取り消され、前に言い渡された拘禁刑を受けなくてはならないことになります。
また、刑事裁判で有罪の判決を受けるということは、社会的には大変厳しい制裁を科されることになります。
公的な資格には、有罪判決を受けた人に対して、一定期間資格を制限しているものもあります。
執行猶予の期間中は、パスポートの取得が制限されることがあります。
さらに、アメリカなど、薬物犯罪事件での逮捕歴のある人には入国許可が出にくい例もあります。
【初度の執行猶予の要件】
- 過去に1度も拘禁刑以上の刑の確定判決を受けていないこと
- 過去に拘禁刑以上の執行猶予付きの確定判決を受けたことがあるが、今回の判決言渡し時点で猶予期間が経過していること
- 過去に拘禁刑以上の執行猶予付きの確定判決を受けたことがあり、かつ、今回の判決言渡し時点で猶予期間が経過していないが、今回判決が言い渡される犯罪が執行猶予判決確定前の犯行であること
- 過去に拘禁刑以上の実刑の確定判決を受けたことがあるが、最後の刑の執行終了日又は執行免除日から今回の判決言渡し時点で5年を超えていること
- 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しをするとき
- 情状により執行猶予に付することが相当であること
※①~④のいずれかの場合であって、かつ⑤⑥の場合、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができます。
【再度の執行猶予の要件】
執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われています。
しかし、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。
法律上、
- 2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け
- 情状に特に酌量すべきものがある
- 再度の執行猶予期間中における犯行ではない(保護観察の仮解除中を除く)
という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について再度執行猶予判決を得ることが可能となります。
執行猶予制度の改正
改正刑法に基づき、2025年6月1日から、新しい執行猶予制度が施行されています。2025年6月1日以降の事件に適用される新しい執行猶予制度の主な改正点は以下になります。
1 再度の執行猶予の条件緩和
これまでは、1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合のみ、再度の執行猶予が可能でした。
改正後は、2年以下の拘禁刑(懲役と禁錮の一本化)を言い渡す場合にも、再度の執行猶予が可能になります。
拘禁刑の上限が1年から2年に引き上げられたため、再度の執行猶予の対象となる刑の幅が広がります。
2 保護観察付執行猶予中の場合の再度の執行猶予
改正前は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合、再度の執行猶予は不可能でした。
改正後は、保護観察付執行猶予中に再犯した場合でも、再度の執行猶予が可能となります。
ただし、再度の執行猶予期間中に再犯した場合は、保護観察の仮解除中を除き、さらに再度の執行猶予を付すことはできません。
3 執行猶予期間満了後の再犯の場合の効力継続
執行猶予期間中の再犯について公訴が提起された場合、執行猶予期間満了後も一定の期間は、刑の言渡しの効力及びその刑に対する執行猶予の言渡しが継続しているものとみなされます。
これにより、いわゆる「弁当切り」(前刑を失効させるために公判の引き延ばしをする行為)はできなくなったと考えられます。
薬物犯罪における特殊性
薬物犯罪ではシンナーの使用等ごく限られた場合を除き、罰金刑のみで処罰されることはありません。したがって、執行猶予をとれるかどうかが大きな分かれ道になります。
もっとも、薬物の使用で公判請求されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される場合がほとんどです。
例えば、覚醒剤使用の初犯であれば、拘禁1年6月、執行猶予3年となるケースが多いです。
しかし、薬物が禁止されている理由の一つに高い依存性が挙げられますが、薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪といえます。
前に薬物犯罪事件で執行猶予判決となり、その後、その執行猶予期間中に再度薬物犯罪事件を起こした場合には、ほぼ確実に実刑判決が下ります。
制度上は、再度の執行猶予制度がありますが、情状が特別な場合に限られるので、通常、薬物事案で再度の執行猶予は認められることはありません。
執行猶予期間満了後の再犯については、執行猶予期間が満了してからどれくらいの期間が経っているかによって執行猶予がつけられるか否かが変わってきます。
執行猶予期間の満了から1年未満での再犯となると再び執行猶予を得ることは難しいですが、10年以上経過してからの再犯であれば、執行猶予を狙うことも可能です。
しかし、裁判所に対し、執行猶予をすることが妥当であると思ってもらうためには、適切かつ効果的な弁護活動を行わなければなりません。
もちろん、裁判所は法律を扱うスペシャリストであり、それに対抗するには同じく法律のスペシャリストである弁護士が必要であると思われます。
また、薬物犯罪の特殊性にかんがみて、薬物犯罪に精通している又は刑事事件の刑事弁護に強い弁護士に依頼することが望ましいです。
ですので、薬物犯罪の執行猶予についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しておりますので、刑事弁護に自信がありますし、24時間体制でお電話の対応をさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。